人生の最後に、誰もが受けたくなる介護サービスをベネッセ、ノウハウゼロからの挑戦 株式会社ベネッセホールディングス
doda X(旧:iX転職)は、パーソルキャリアが運営するハイクラス転職サービス。今すぐ転職しない方にも登録いただいています。
今の自分の市場価値を確かめてみましょう。
この記事は2013年10月28日に掲載されたものです。
事業の立ち上げに、取締役会は全員反対した、ただ1人を除いて
「たった1人の強い意志が、世の中を変える。時代を動かす」
その言葉がまさに当てはまるのが、1995年、ベネッセ(当時の福武書店)のシニア・介護事業の始まりでした。当時、監査役の1人は、「10本の針に一度に糸を通すようなものだ。それくらい困難で不可能に近い事業展開だ」と言ったそうです。それもそのはず、当時の福武書店のビジネスは、進研ゼミの名で展開していた通信教育など、教育事業が中心。シニア・介護ビジネスには、何の経験もなければノウハウもありません。当時の取締役会は現会長の福武總一郎以外、全員が反対でした。

それでもベネッセのシニア・介護事業は、スタートを切りました。そのエンジンとなったのは、提案者であり、唯一の賛成者である福武の強い意志でした。きっかけは、福武自身のおばあさまの介護に関わる体験。1988年ごろ、身体を悪くしたおばあさまの介護支援を受けるために、福武は市役所にヘルパーさんを頼みに行きました。しかし、1人目2人目と、おばあさまとそりが合わない。ヘルパーさんが家に来る日は朝から落ち着かない様子を見せるおばあさまの態度を見ることもあったそうです。
ようやく3人目で落ち着いたそうですが、うまくいかなかった理由を「老齢者に対する敬意のなさ」ではないかと福武は考えました。例えば、小さなことですが、3人目の方が初めておばあさまを「福武さん」と呼んだそうです。それまでの2人は「おばあちゃん」。何もその呼称が悪いわけではありませんが、どちらが老齢者を個人として尊重をしているかを考えれば、前者なのではないでしょうか?
そんな体験を通して、福武はある思いを抱きます。「この社会をつくり、支えてきたシニアの方々が、人生の最後に受けるサービスを選べず、我慢を強いられるのはおかしい。私たちの手で、この国の介護をもっと良くしていこう」。当時の福武の胸には、1990年から企業CI活動として掲げたベネッセの「よく生きる」という理念が、そのころから強く心にあったと思います。子どもたちの教育だけでなく、年を取るほどに幸せになれる社会づくりに貢献するべきだ。 シニア・介護事業への挑戦は、私たちにとって異端ではなく、むしろ必然だ。そんな使命感が、すべてのスタートでした。
事業分野、立地、呼称、お客様のために、一つの妥協も許さない
それから10年近く経った2000年、日本に介護保険制度が施行されるに伴い、ベネッセは本格的に介護ビジネスに着手することになりました。この事業開始に伴い、その前年の1999年にベネッセの他の事業を担当していたメンバーを数多くこの分野に異動させ、事業開発のスピードをあげることとなりました。実は、私もその時のメンバーの一人でした。
そして、現在では、有料老人ホーム運営数では業界1位を獲得するまでに成長しました。あらためてその要因を振り返ってみると、あらゆることに妥協しなかったことが良かったのではないかと思います。

まず、私たちは、施設介護に力を入れました。介護には大きく分けて施設介護と在宅介護がありますが、在宅介護では、ヘルパーは個々のお客様宅でサービスをするため、本部で内容をチェックすることができません。お客様一人一人の満足度を、本部がこの目と耳で確かめるために、施設介護に絞りました。
立地も重視しました。私たちが施設介護運営に本格的に乗り出す2000年以前、地価の高い東京都心部には施設はほとんどありませんでした。そんな中、私たちはあえて都市部、住宅地を中心に施設を展開しました。なぜなら、高齢者が増えているのは主に都市部だったからです。介護施設はお客様にとって、 生活の場そのものです。運動場やイベントホールとは違います。ならば、お客様が施設の都合に合わせて生活の場を郊外に移すのではなく、慣れ親しんだ都市部に施設をつくるべきだと考えたのです。

介護サービスの呼称にも、ベネッセ独自の発想があります。介護サービスの利用計画のことを、通常は「ケアプラン」と呼びますが、私たちの施設でそういう言い方はしません。「生活プラン」と呼びます。というのも、介護は、お客様の生活の一部分ではなく、生活まるごとの質を高めるサポートだと考えているからです。その方がこれまでどんな人生を歩んでこられたのか。なぜこの施設に入居されたのか。どんな趣味趣向を持っていらっしゃるのか。お客様の生活に関するあらゆる情報を把握した上で、お客様一人一人に合ったサービスを提供し続けています。
スキルや経験ではなく、 思いを共感できる人とともに
他施設との差別化を明確にし、ぶれなかったことで今まで続けてこられたシニア・介護事業ですが、立ち上げにあたって最も苦労したのは、人材の採用と育成でした。そもそもベネッセグループ内部には、施設運営の経験もなければノウハウもありません。しかし、私たちはここでも介護業界の常識にとらわれない発想で、人材の採用、育成に取り組みました。
採用において、重視したのはスキルや経験ではありません。ベネッセの「既存の介護ビジネス観を変えていく」というマインドに共感してくれる人材であること。これが、採用における第一の基準でした。スキルは、入社後に身に付けることができます。しかし、マインドの部分はそうはいきません。だから、業界の古い慣習に染まっていない、意志をともにできる「同志」と呼べる人たちを数多く採用したのです。
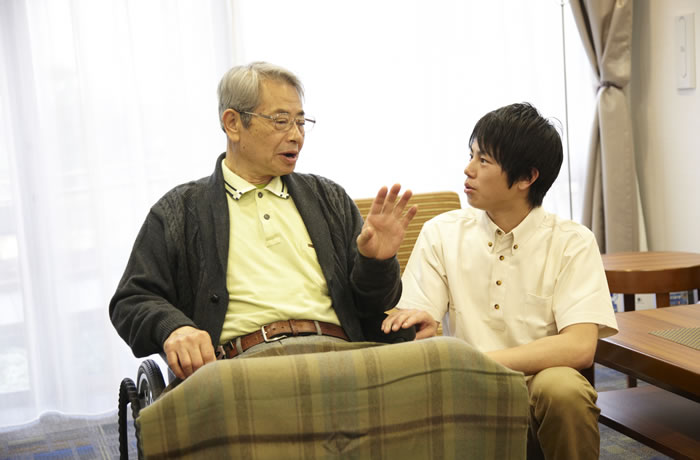
2000年には、事業の成長を加速させるため、大きな決断もしました。ベネッセ本体からの独立です。株式会社ベネッセケアという名称の別法人を設立し、それが2003年に現在の株式会社ベネッセスタイルケアへと発展しました。独立を決めた理由は、大きく2つです。1つは、意思決定のスピードを上げるため。もう1つは、独自の人事制度を確立するためです。
介護ビジネスの価値を生み出すのは、他ならない現場のスタッフたちのサービスです。しかし、通信教育事業を中心に組まれてきたベネッセの人事制度では、シニア・介護事業の現場スタッフたちが中心の制度にはなりえません。継続的なサービスの質向上のためには、個々の知識やスキルはもちろん、おもてなしの姿勢まできちんと評価できる、介護ビジネスならではの人事制度が必要不可欠だと考えました。そこで独立を果たしました。さらに、2007年には、当時まだ30億円弱ほどしか利益がなかったにもかかわらず、人事制度を見直し、整備する費用に、約7億円をかけました。一人一人がモチベーション高く働ける組織としてのインフラを整備することが、何より優先すべき投資だと考えたからです。

成長できたのは、会社だけではなく、私自身も シニア・介護事業に出会えて、本当に良かった
事業を成長させていく過程で、たくさんの失敗をし、たくさんの感動をいただきましたが、そのおかげで、事業責任者であった私自身も大きく成長することができたと思います。この事業に関わる前、私は通信教育ビジネスにしか携わったことがありませんでした。そして、シニア・介護事業の担当になることへの抵抗が、正直少しありました。しかし現場にやってきて、その考えは吹っ飛びました。初めてお客様と対面するビジネス。リアリティーが違いました。お客様から直接「ありがとう」をいただく喜びを、実感することができました。

しかし、それ以上にお叱りを受けたときこそ、自分や仕事を成長させる機会だったと思います。シニア・介護事業というビジネスの特性上、私たちのサービスは、お客様の人生において最後に受けるサービスになる可能性も大いにあります。そんなお客様やそのご家族に満足いただけなかったときの悔しさや悲しみは、他のビジネスでは味わえないほど大きく苦しいものでした。
施設入所から、入居者さまが亡くなられた後もずっと、私たちの施設に入所させたことを後悔されているお客様がいらっしゃいました。私たちの介護が特別に不十分であったわけではなかったとは思っていますが、大切なのは提供者の満足ではなく、お客様の満足です。その意味では、私たちのサービスはそのお客様にとっては0点でした。悔やんでも悔やみきれませんが、当時の私にできたことは、命日にお墓に行かせていただき手を合わせ、残されたご家族のお気持ちに寄り添うことだけでした。お客様の「よく生きる」を支援するはずのベネッセが、お客様にこんなつらい思いをさせている。その事実は、シニア・介護事業からの撤退も考えさせられるほど、私の心に残りました。
でも、そんな失敗があったからこそ、「もう次はお客様にこんな思いをさせるわけにいかない」と奮起して頑張ることができたのだと思います。シニア・介護事業が成長した以上に、私自身が一人の人間として大きく成長できた気がします。
教育機関への参入、新型施設、「トータルシニアリビング」 まだこの国にない、新しい介護のかたちを
ベネッセグループとしてのシニア・介護事業を確立できた現在、私たちの視線の先にあるのは、この国の介護業界全体の質の向上とさらなる発展です。そのために新しく取り組んでいることが2つあります。1つは、教育機関との連携。もう1つは、介護施設と保育施設の融合です。

まず、教育機関との連携についてですが、これまで手に入れた経験とノウハウを今度は、これからの介護業界を担う人たちに還元していこうと考えていま す。2009年、愛媛女子短期大学(現:環太平洋大学短期大学部)にベネッセスタイルケアコースを新設しました。ここ数年、介護福祉関連の学部が数多く設 置されましたが、ほとんどの授業が介護の歴史や理論を教えるにとどまっていました。その原因は、教える側に現場経験がないためです。そこで、ベネッセスタ イルケアコースには、当社のスタッフたちを派遣し、机上の理論ではないリアルな介護を教えています。
現場での苦労話や、お客様に喜んでいただいたエピソードなど、現場を誰よりも知る私たちだからこそ伝えることができる介護という仕事のやりがいと意義を語る。学生が就職し、介護現場で働き出した際に、ギャップやミスマッチをなくしていきたい。この動きを、全国の大学や短大で少しずつ広げていければと思っています。
次に、介護施設と保育施設の融合についてです。2008年には、介護と保育を融合させた複合施設「くらら大泉学園」と「ベネッセチャイルドケアセンター大泉学園」をオープンさせました。子どもたちとシニアの方々の世代を超えたふれあいの場をつくることで、初めて家族以外のコミュニティーに出る子ども たちの社会性を育み、同時に、シニアの方々には毎日の生活に新しい刺激と喜びを提供できる施設にしたいと考えています。
その先にある私たちのビジョンは、「トータルシニアリビング」という考え方です。シニアの方々、一人一人が自分らしく生きていけるような地域コミュニティーを、あらゆる側面から総合プロデュースしていこうという宣言です。介護施設の運営はもちろんのこと、在宅介護を受ける方々を対象にした宅配弁当サービス、介護用品のレンタルサービス、さらには地域で訪問診療を行うドクターの開業支援サービスまで。これまでになかったシニア・介護ビジネスの広がりをつくっていきたい。シニア・介護業界の新しいスタンダードとなる取り組みを、これからも続けていきます。
最も大切なのは、人と、社会と、どう向き合うか
事業創設から約20年。シニア・介護ビジネスのノウハウも経験もまったくない状態から、日本の介護業界を支える企業の一つにまで急成長を遂げることができました。その最大の原動力は、「この社会をつくり、支えてきたシニアの方々のために、この国の介護をもっと良くしていきたい」という理念を本気で実現しようとした設立メンバーたちの思いと、現場スタッフ一人一人の頑張りに他ならないと思います。

現在、インターネットやSNSなどをはじめとした、さまざまなデジタルコミュニケーションやITサービスが世の中に普及し続けています。しかし、コミュニケーションの手段やツールの進化ばかりに気を取られ、私たちは本来もっとも大切にすべき本質的な価値を忘れていないだろうか、という危機感も同時に感じます。本質的な価値とは、「いかに目の前のお客様に喜んでいただき、感動していただけるか」という思い。あらゆるサービスの根っこにあるものです。例えば、ゲームを開発するエンジニアにとって技術スキルももちろん大切ですが、それ以上にゲームを通じて、「ユーザーに何を感じてもらうか、世の中にどんな 価値を提供したいか」という、人と社会に真剣に向き合う姿勢が大切なのではないでしょうか。
それはベネッセグループも同様です。教育事業、シニア・介護事業、その他の事業。どれをとっても、私たちのビジネスの中心には常に「人間対人間の関わり」があります。シニア・介護事業を通じて、お客様一人一人と向き合い、さらなる進化を遂げていきたい。誰もが人生の最後に受ける介護サービスを、受け ざるをえないサービスから、受けたくなるサービスへ。私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。
PROFILE

- 小林 仁(こばやし・ひとし)
株式会社ベネッセホールディングス 取締役 グループ経営企画本部長 - 1960年生まれ。1985年に福武書店(現ベネッセ)に入社。2000年、ベネッセケア取締役に就任し、介護施設の本格展開を指揮する。2007年、ベネッセスタイルケア代表取締役社長に就任、2013年7月1日付、退任。現在は、ベネッセホールディングス取締役グループ経営企画本部長。
今すぐ転職しなくても、
まずは自分の市場価値を確かめて
みませんか?
変化の激しい時代、キャリアはますます多様化しています。
ハイクラス転職サービス「doda X(旧:iX転職)」に登録して、
ヘッドハンターからスカウトを受け取ってみませんか?

